 賃管士について調べている人
賃管士について調べている人賃貸不動産経営管理士試験の合格率・難易度・必要な勉強時間や必要な理由を知りたいな。
他の不動産に関する資格との比較も知りたい。
賃貸不動産経営管理士は、賃貸不動産のアパート・マンション・テナントなどの管理に関する資格です。
当記事では、賃貸不動産経営管理士試験の概要(合格率、難易度、勉強時間、資格が必要な理由、他の不動産資格との比較)について解説します。
特に、2021年6月度より一定規模以上の賃貸不動産の管理会社は、国土交通省への登録が義務化されることになります。
登録制度の義務化によって、賃貸不動産経営管理士資格は管理会社にとって必要な資格となります。
賃貸不動産経営管理士試験は、難化が予想される試験です。受験をお考えの人は、ぜひ最後まで読んでください。
試験・資格のことを知ることが受験を考えている人にとって、合格への第一歩となります。
確実に合格したいという人には通信講座という方法がおすすめです。
»【2022年・オンライン講座】賃貸不動産経営管理士の通信講座おすすめ厳選3選
»【合格率70.25%】アガルートの賃貸不動産経営管理士通信講座【口コミ・評判】
»【合格率70.25%!】賃貸不動産経営管理士のアガルート通信講座を徹底レビュー
»【口コミ・評判】スタディングの賃貸不動産経営管理士通信講座はスマホに特化!
賃貸不動産経営管理士試験の概要【合格率・難易度・勉強時間・必要な理由】

賃貸不動産管理の業界については、2020年6月12日に「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律案」が可決されました。
賃貸不動産経営管理士は、2021年度試験より国家資格となりました。賃貸不動産に携わる場合に必要な資格という位置付けになりますので、受験を考えている人は早めの取得をおすすめします。
賃貸不動産経営管理士とは?

賃貸不動産経営管理士の資格について解説します。
以下、賃貸不動産経営管理士協議会のHPより引用します。
賃貸不動産経営管理士とは、主に賃貸アパートやマンションなど賃貸住宅の管理に関する知識・技能・倫理観を持った専門家です。
賃貸住宅は、人々にとって重要な住居形態であり、その建物を適正に維持・管理することは人々の安心できる生活環境に直結します。
そのため、継続的かつ安定的で良質な管理サービスに対する社会的な期待や要望は多く、賃貸不動産の管理業務にかかわる幅広い知識を有する賃貸不動産経営管理士の活躍が期待されています。
引用元:賃貸不動産経営管理士協議会
簡単にいうとアパート・マンション・テナントといった賃貸不動産についての管理業務で、入居から退去までの管理全般を行うために必要な知識等を習得して活躍するための資格です。
具体的な業務としては、下記の内容があります。
・入居者の家賃収受
・入居者の苦情などの問合せ窓口
・建物の維持修繕
・賃貸借契約の更新
・賃貸借契約の解約業務
・退去後のリフォーム
賃貸不動産管理会社が行っている業務ともいえます。
賃貸管理会社については、自社で賃貸仲介(客付け)を一体として行っている会社と、賃貸仲介は、他会社に依頼している会社があります。
賃貸不動産管理会社の最終的な目的としては、上記の業務を通じて家主の収益の最大化を図ることです。
賃貸不動産経営管理士は、専門的な知識を通じてこれらの業務を行います。
賃貸不動産経営管理士の試験について

賃貸不動産経営管理士試験の内容について解説します。
試験日程
例年、11月の3週目の日曜日が試験日となります。
2023年度は11月19日(日)に実施予定です。
| 2023年度の試験日程 | |
| 受験申込案内配布期間 | |
| 受験申込受付期間 | |
| 試験日 | |
| 合格発表日 |
受験申込は、必要書類を郵送となります。
年に1度の試験で、2020年度試験より出題数が50問に増えたことにより、試験時間が120分になりました。(従来は出題40問で90分の試験)
試験地
試験地は、北海道、岩手、宮城、福島、群馬、栃木、茨城、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、石川、長野、静岡、岐阜、愛知、三重、滋賀、奈良、京都、大阪、兵庫、島根、岡山、広島、山口、香川、愛媛、福岡、熊本、長崎、大分、鹿児島、沖縄 (2022年度)の全国35地域で実施です。
受験申込時に試験地を選ぶことはできますが、試験会場までは選べませんので、受験票が届くまで受験会場はわかりません。
受験会場については、以下の記事で解説しています。
»賃貸不動産経営管理士の試験会場はどこ?過去の受験会場を解説
受験要件
賃貸不動産経営管理士試験を受験するために、特別な要件はありません。
年齢、性別、学歴など関係なく誰でも受験できます。
受験料
13,200円(税込)
資格試験の受験料に対する消費税の取扱については以下の記事で詳しく解説しました。非課税の理由を知りたい方は参考にしてください。
»【課税・非課税】資格試験の受験料と消費税の関係【国家資格・民間資格】
試験の出題範囲
- 管理受託契約に関する事項
- 管理業務として行う賃貸住宅の維持保全に関する事項
- 家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理に関する事項
- 賃貸住宅の賃貸借に関する事項
- 法に関する事項
- 1から5までに掲げるもののほか、管理業務その他の賃貸住宅の管理の実務に関する事項
※問題中法令に関する部分は、令和3年4月1日現在施行されている規定に基づいて出題する。ただし、「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」に関しては、施行前の事項についても出題することがある。
出題形式・出題数
・出題数は50問
出題形式は、4つの選択肢から1つを選びマークシートに記入する方式です。
出題数は50問あります。(免除者は45問)
免除制度について
賃貸不動産経営管理士の試験は、一部免除という制度があります。
おおむね夏頃に開催される免除講習を受講し、修了することにより本試験の5問が免除となる制度です。
簡単にいうと、免除対象の5問は解答しなくても満点扱いとなります。
免除制度については以下の記事で詳しく解説しています。
»賃貸不動産経営管理士試験の5問免除講習
合格率の推移
賃貸不動産経営管理士試験は、2013年度より多肢選択式マークシートの試験として始まりました。
2012年以前については、講習を受講して最後に試験を行い一定点数以上で合格という方式で、よほどのことがない限り合格できました。
2013年以降の試験結果について申込者数、受験者数、合格者、合格率をまとめましたのでご覧ください。
| 年度 | 申込者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 合格点 |
| 2013年 | 4,106 | 3,946 | 3,386 | 85.81% | 28(40問中) |
| 2014年 | 4,367 | 4,188 | 3,219 | 76.86% | 21(40問中) |
| 2015年 | 5,118 | 4,908 | 2,679 | 54.58% | 25(40問中) |
| 2016年 | 13,862 | 13,149 | 7,350 | 55.90% | 28(40問中) |
| 2017年 | 17,532 | 16,624 | 8,033 | 48.32% | 27(40問中) |
| 2018年 | 19,654 | 18,488 | 9,379 | 50.73% | 29(40問中) |
| 2019年 | 25,032 | 23,605 | 8,698 | 36.85% | 29(40問中) |
| 2020年 | 29,591 | 27,338 | 8,146 | 29.8% | 34(50問中) |
| 2021年 | 35,553 | 32,459 | 10,240 | 31.5% | 40(50問中) |
| 2022年 | 35,026 | 31,687 | 8,774 | 27.7% | 34(50問中) |
開始2年間はボーナスステージでしたが、年々、受験者は増加するとともに難易度があがり合格率が低くなる傾向にあります。
特に2019年年度は、合格率も36.8%となり、2020年度はついに合格率30%を切るところまで絞られるようになりました。2022年は、合格率27.7%という結果です。
過去問をみると、問題自体も難しくなっています。
難しくなっている原因として、正誤の組み合わせや個数問題が増えていることがあげられます。
試験が始まったころは、たいして勉強をしなくても合格が可能でしたが、今では、しっかりと対策して勉強をしなければ、合格はできない試験になりました。
登録について
・管理業務に関し2年以上の実務の経験を有する者
・国土交通大臣がその実務の経験を有する者と同等以上の能力を有すると認めた者
【登録料】
・6,600円(税込)
賃貸不動産経営管理士試験合格者が賃貸不動産経営管理士として登録をするには、2つのうちどちらかの要件を満たす必要があります。
1、管理業務に関し2年以上の実務の経験を有する者
2、国土交通大臣がその実務の経験を有する者と同等以上の能力を有すると認めた者
2については、簡単に言うと実務に代わる講習を修了することです。
2020年度以前の試験では、登録要件に宅建士という方法もありましたが、新制度になるため、宅建士の要件はなくなり、2年の実務経験に代わる実務講習が新設されます。
登録料は、6,600円(税込)です。
これは、賃貸不動産経営管理士として登録するために必要な料金です。
他不動産3資格との比較

・管理業務主任者
・マンション管理士
宅地建物取引士、管理業務主任者、マンション管理士は、管理業務主任者と親和性のある資格です。
4つの資格を簡単な内容と勉強時間の目安で比較表にしました。
| 資格名 | 関連の不動産業種 | 合格率 | 勉強時間の目安 |
| 賃貸不動産経営管理士 | 賃貸物件の管理会社 | 27.7% (2022年) |
150時間 |
| 宅地建物取引士 | 宅建業者(仲介・売買) | 17.0% (2022年) |
300時間 |
| 管理業務主任者 | マンション管理会社(分譲) | 19.4% (2021年) |
250時間 |
| マンション管理士 | マンション組合のコンサル | 9.9% (2021年) |
600時間 |
上記の勉強時間の目安は、初学者がゼロから始めた場合です。
それぞれ重複する出題分野があるので、宅建士の人が賃貸不動産経営管理士を受験するなどの場合には、目安の学習時間は少なくなります。
4つの資格から比較すると、賃貸不動産経営管理士の難易度は、易しい部類に入ります。
しかし、これはあくまでも2022年度の結果だと思ってください。
成熟された宅建士の資格や管理業務主任者、マンション管理士の資格は、今後も似たような推移になると予想されますが、賃貸不動産経営管理士は、難化傾向にあります。
特に賃貸不動産経営管理士は、2021年度に国家資格となりました。
今後、合格率も20%程度にまで難化して、管理業務主任者と同等程度の難易度になっていく可能性はあるかと思います。
そのため、比較的容易に合格可能なうちに取得されることをおすすめします。
賃貸不動産経営管理士が必要な理由

2021年6月に施行される「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」により、一定規模以上(管理戸数200戸以上)の賃貸不動産の管理会社は、事務所ごとに業務管理者が1人以上必要となります。
業務管理者は、賃貸住宅の管理業務について安定して円滑に業務が行われるために必要とされる人です。
この業務管理者になるために必要な資格が賃貸不動産経営管理士なのです。
他に宅地建物取引士も必要な講習を受講することにより業務管理者になることができます。
つまり、賃貸物件の管理会社には業務管理者が必要=賃貸不動産経営管理士が必要という図式になるということです。
法律が施行されて猶予期間はありますが、業務管理者がいなくては賃貸物件の管理会社は営業ができなくなるため、管理会社で働く上で必須となる資格と言えます。
業務管理者については、以下の記事で詳しく解説しています。
»宅地建物取引士・賃貸不動産経営管理士が業務管理者となるための要件
まとめ
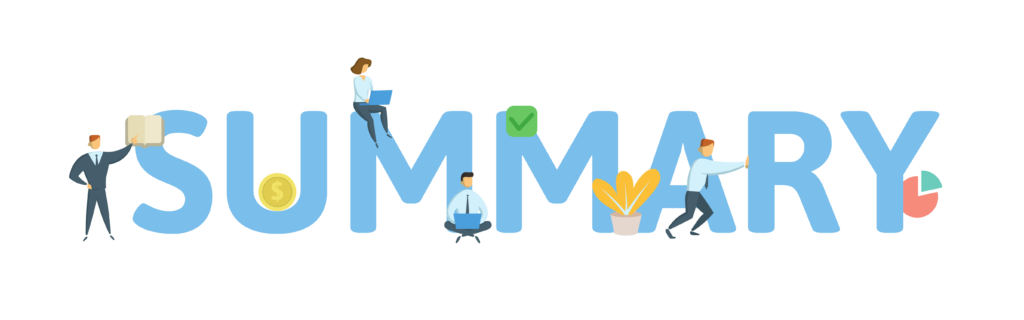
・賃貸不動産経営管理士試験は難化傾向
・賃貸物件の管理会社に必要な業務管理者になれる
・2021年国家資格化
・資格手当がつく
賃貸物件の管理については、幅広い知識が求められます。賃貸不動産経営管理士は、賃貸管理に必要な知識を備えた専門家といえます。
賃貸不動産経営管理士試験は、近年難化傾向にあります。今後も合格率は低く推移していくと予想されます。
初学者が合格を目指すとき、勉強時間は150時間が目安となります。
(もちろん個人差はあります。)
今後、賃貸管理会社は、事務所ごとに業務管理者が必要となり、業務管理者になることができる賃貸不動産経営管理士は必要とされます。
賃貸物件の管理会社では、賃貸不動産経営管理士や宅地建物取引士の資格を有している従業員に資格手当を支給している会社が多いです。
合格を目指そうと考えている人は、比較的容易な今のうちに取得されることをおすすめします。
絶対に合格したいという人には通信講座という方法がおすすめです。
»【2023年・オンライン講座】賃貸不動産経営管理士の通信講座おすすめ厳選2選
»【合格率70.25%】アガルートの賃貸不動産経営管理士通信講座【口コミ・評判】
»【合格率70.25%!】賃貸不動産経営管理士のアガルート通信講座を徹底レビュー
»【口コミ・評判】スタディングの賃貸不動産経営管理士通信講座はスマホに特化!
賃貸不動産経営管理士に合格するためのロードマップは以下の記事で解説しています。
»【完全版】賃貸不動産経営管理士試験に合格するためのロードマップを徹底解説

